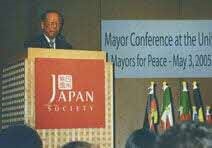廿日市市
戦争体験記
被爆市長として思うこと
【山下 三郎 氏の紹介】
山下さんは被爆当時15歳、旧中学校の4年生で学徒動員として広島市内の工場で作業に従事中、爆心地から約4.5㎞地点で被爆しました。幸いにもけがはなく、その後昭和30年の宮内村議会議員当選以降、廿日市町議会議員、廿日市市議会議員を経て、平成3年から平成19年まで4期16年の間、廿日市市長を務められました。市長在任中は、被爆市長として「反戦・非核・平和」をテーマとした活動にも力を入れて取り組まれました。
昭和17年4月、宮内村(現廿日市市宮内)に住んでいた私は、母とともに夜明け前の薄暗い道を歩き、郊外電車と市内電車を乗り継ぎ、希望に胸をふくらませ旧制山陽中学校(爆心地より約1.2km)の正門をくぐりました。一年間は楽しく学校に通いましたが2年生になると水害復旧作業や、軍需工場への動員が日に日に増えてきました。
そして3年生の昭和19年6月からは、広島市南観音町の三菱重工業広島機械製作所へ学徒勤労に動員されました。
昭和20年8月6日の朝、その日は雲一つない暑い日でした。4年生になった私はいつも通り朝7時30分より工場の天井クレーンに乗り操作をしていました。
すると、突然「ピカッ」と稲妻の何十倍もの強烈な光が窓から見え、同時にクレーンが止まりました。工場の変電所が爆破されたのかと思っていた次の瞬間「ドーン」という大音響とともに、強烈な風圧で工場のガラスや屋根の一部が吹き飛びました。私は無我夢中で高い天井から鉄柱を伝わって降り、防空壕めがけて突っ走りました。防空壕にはガラスの破片で血だらけの友人や、足を引きずる人などが集まっており、皆家族のことを心配しパニック状態に陥っていました。
午前10時過ぎに「広島市内は、新爆弾で火の海だ。各自、家に帰るなり避難するなりせよ。」との命令が出て、私は自宅に帰ろうと工場を出ましたが、そこはまさにこの世の生き地獄でした。即死を免れた被災者が、広島市内中心部から郊外へ向けて救助を求め、どんどん避難していました。皆、おし黙ったまま、男女の区別も判らないほど真っ黒い顔をし、皮膚が焼け、裂けて、垂れ下がっています。誰一人として、まともな衣服を着けておらず、上半身は裸で、ズボンは黒く汚れ、しかもボロボロに裂けていました。
途中、何千人にも及ぶ瀕死の被災者を目の当たりにしましたが、私にはどうしてあげる こともできませんでした。こうした方々のほとんどは、その場で、あるいは逃げる途中、 さらには郊外の救護所で、家族と離ればなれのまま息を引き取ることになりました。
たった一発の原子爆弾の投下で、一瞬のうちに美しい広島の街は廃墟と化し、子どもや高齢者を含む何十万人の市民が命を落としたのです。
また、原爆投下後、犠牲となった肉親を探すために広島市内へ入り、残留放射能による被爆(入市被爆)で現在も後遺症に悩まされている人も多くいます。
私も何度か広島市内に入りましたが、そこは見渡す限り焼け野原で、家も木も電柱も消え何一つ残っていない光景が広がり、わずかに、近代的な鉄筋の建物がところどころ残っているだけでした。今まで見ることができなかった広島市内全域が、一望できるのです。
そこに残っていた建物の一つが、現在の原爆ドームです。私はこのときほど、虚しく、悲しい感慨にとらわれたことはありませんでした。
昭和20年8月15日正午、音響の悪いラジオで日本の敗戦を知りました。音声が聞き取りにくく、何を喋っているのかすぐにはわからなかったのですが、我が国が戦争で敗れたことはおおよそ理解できました。「神風日本は本土決戦で戦争に勝つ」と教えられていたものの、心の中では本当かなと疑心暗鬼でいました。それでもやはり、敗れたかと思えば、涙があふれ、止まりませんでした。そして茫然としたまま暑い一日が暮れました。
幸いにして生き残った私の使命は、市民の非核・平和への願いを実現するため、私の体験を通じて、核兵器使用の悲惨さと平和の尊さを、世界中の人々に、そして次の世代の若者たちに伝えていくことだと思っています。
将来を担う子どもたちに、焼け野原ではなく、美しい地球を残し、安心して暮らし続けることができる環境をつくり、引き継ぐことこそが今を生きる我々の責務であると思いま す。世界中のあらゆる人々に、核兵器使用の悲惨さと地球全体に及ぼす脅威の認識、そして、製造・所有することの無意味さを知ってほしいと思います。