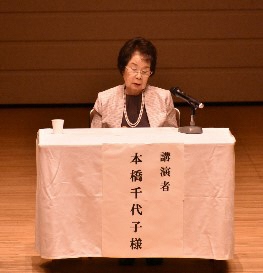練馬区
戦争体験記
平和祈念コンサートでの戦争体験講和
本橋さんは、現在の練馬区貫井にあたる貫井町で生まれ、太平洋戦争の間も離れることなく、現在も練馬区に在住されています。練馬区において毎年実施している平和記念コンサートにおいて、下記の戦争体験をお話ししていただきました。
小学校に入学したのは戦時中の昭和16年ごろで、今の練馬第二小学校、当時は練馬第二国民学校であった。
昭和16年12月8日の日米開戦後は、お金があっても品物がなく、衣類なども切符が無いと買えず、食糧なども配給制度になった。
金属も回収となり、何もない方はお鍋やお釜まで出した。その金属で、飛行機、軍艦、鉄砲の玉など、いろいろなものに使用されたそうである。私たちは、「欲しがりません。勝つまでは。」と我慢したものだった。
昭和19年になると、東京の空にも米軍のB29がやってきた。警戒警報が放送されると、防空頭巾をかぶり、空襲警報にならないうちに鞄を背負い、上級生は下級生の面倒を見ながら、急いで家に帰った。カバンや防空頭巾には、氏名、住所、血液型を書いて、縫い付けて背負っていた。
昭和19年には集団疎開が始まり、昭和20年3月になると、練馬第二小も集団疎開に行くことになった。疎開先は群馬県の玉屋旅館だったそうである。疎開しない方や、田舎の親戚に行った方、いろいろだったが、学童疎開は3年生以上だった。
私はどこにも行かなかった。東京が全滅するという噂が流れていたため、当時消防団長をしていた父は、「集団疎開に行った10歳にも満たないお前が生き残り、東京の家族が全員死んだらどうやって生きていくの、死ぬときは一緒だから、お前は疎開に行かなくていい」との一言だった。
このころには、もう昼夜を問わず空襲が始まっていた。夜、空襲が恐いので、寝巻きなどには着替えないで、そのまま枕元にカバン、くつ、学用品などを置いて、空襲警報が鳴ったらすぐ防空壕に逃げ込めるようにして寝ていた。電灯には黒い布を被せ、光が漏れないようにしていた。
昭和20年3月10日の東京大空襲では、東の空が真っ赤で、すごかった。私は家で留守番をしていたが、姉たちは勤労奉仕で兵隊さんの軍服のボタン付けなどをしていたそうである。
高松には、今の練馬中学校のところに陸軍の電信学校があり、東側には高射砲陣地があった。B29が来ると高射砲を撃つのだが、高さが届かず、飛行機は悠々と飛んでいってしまった。
昭和20年5月25日午後10時22分ごろ、B29二百数十機が来て、各地に焼夷爆弾を落とし、このとき、練馬第二小の校庭の真ん中に9キロ爆弾が命中し、校舎が全焼して、コンクリートの土台と西のトイレだけが残った。その火の粉が移り、地元のお寺の円光院が全焼してしまった。一時期は焼け残りの土台で勉強した。その時の写真が今でも残っている。
当時の防空壕は、農業をしている家が多くあったので、自分の土地に防空壕を掘っていた。中は暗くて、ろうそくやランプをつけて、子供たちは本などを読んでおとなしくしていた。土地はあっても、防空壕をつくってくれるお父さんが出征し、つくれない方は、近所の防空壕に入れていただいていた。そのころのお父さんやお母さんは、畑仕事をしながら空襲に備え、子供らは、よく家のお手伝いをしていた。
私の家は農家だったので、食べるものにはそれほど不自由はしなかったが、他の方は食べる物がなくてお腹を空かせていた。農家でも、自分で作ったものでも好きにできない。国からいくらぐらい出すようにと言われ、残ったものを自分たちが食べていた。
食事は、お米に麦が入っていたり、さつまいもを入れたりしたご飯を食べた。野菜は煮たり、ゆでたり、てんぷらにしてよく食べた。お魚は、おじさんが自転車で売りに来てくれたが、そのときだけで、今のようにいつもは食べられなかった。
男の子はベーゴマやけん玉、女の子は鬼ごっこ、石蹴り、お手玉、縄跳びなど、品物がなかったので、自分たちでつくったり、石を拾ったりして遊んだ。
昭和20年8月15日。とても暑い日であった。「天皇陛下の大切なお話があるのでラジオの前に集まるように」と言われて、近所の方も集まってきた。陛下のお話が終わったが、私には何のことかわからなかった。大人の方は泣いていた。後ほど、大人の方から、日本が負けたと言われた。終戦となり、日本が勝つと思って頑張ってきたので、皆さん気が抜けてしまって、仕事が手につかなかったようだ。学校の教科書は、軍国主義はいけないと悪いところを墨で黒く塗った。
昭和20年9月1日、勉強するにも、学校が焼けて教室がなく、都立四商の空き教室を借りて疎開から帰ってきた方たちと勉強した。その後、新しい教室ができて、5年生までは練馬第二小学校に戻ったが、6年生2クラスだけ四商に残り、私たちは新校舎には入れなかった。それでも教室が足りないので、一クラスを半分に分けて、午前の部、午後の部と、二部制で授業を受けた。こんな時代でしたので、みな助け合って勉強していた。
食料事情が悪いので、生徒の体格をよくするために、と給食が出た。当時、練馬第二小から四商まで給食を届けてくれた用務員さんには申し訳ないが、脱脂粉乳を飲んだことがなかったので、あまりおいしくなかったことが印象に残っている。
小学校時代には、いろいろなことがたくさんあったが、昭和23年3月25日、全員小学校を卒業することができた。四商にはお世話になり、とてもいい学校であった。
物のない時代で、練馬第二小を背景にした写真には、ガラスに「練二」、「練二」と書いてあった。卒業当時は物資が不足していて、ガラスが盗まれることがあるため、書いてあったそうである。ガラスが割れると、ガラスがなく、すぐに張り替えられなかったので、板を張ったり、新聞紙を張ったりした。
楽しいこともあったが、戦争という辛く悲しい体験はもう二度と経験したくない。今の子供たちには、私が体験したような辛く悲しいことを味わわせることのないよう、また、この平和な時代が長く続くことを願いながら、私の話を終わりにしたいと思う。