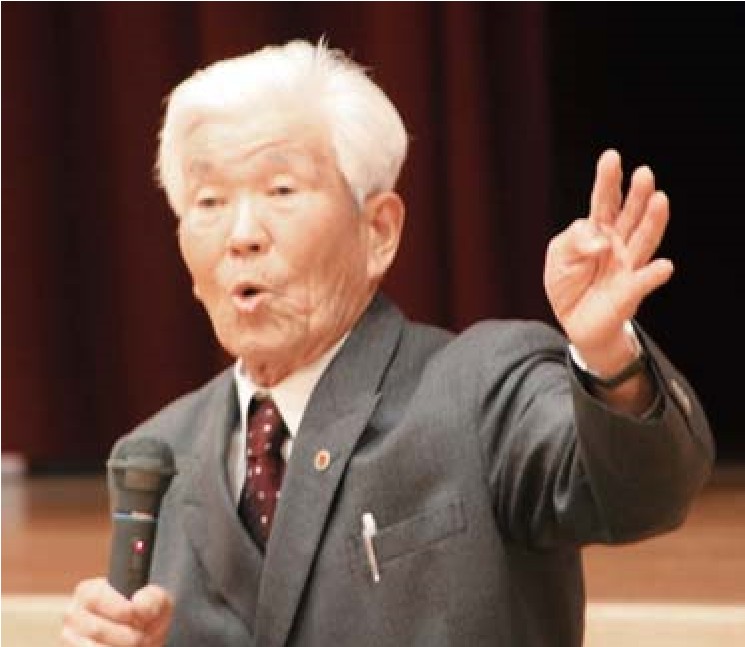川辺町
戦争被害の状況
食糧・物資不足を極めた生活
政府が定めた「国家総動員法」や、「物資動員計画」により国民生活の全部分が政府の統制下に置かれることで、経済活動の停滞が余儀なくされました。食糧増産に拍車が掛けられ、兵役徴兵などによる労働力不足も加わり、食糧生産の活動は低下を辿るばかりでした。また、軍事生産業が最優先されることで化学肥料が欠乏したことも相まって、衣食についても事欠く状態でした。国民服や衣料品などは配給制度(1人年間100点)となっており、容易に入手することもできませんでした。食糧についても同様に入手することができない状態であり、食糧確保のため空地や学校の運動場は一面に耕され、サツマイモなど、農作に明け暮れる毎日でした。
本土空襲の際は名古屋・岐阜などの上空が、赤々と映えるのがよく見え、生きた心地もなくじっと眺め続けるばかりでした。

戦後の復興の歩み
インフレと食糧危機からの復活 ~明るさはまずまちから~
戦後の物資不足とインフレの高まりは想像を絶するものでした。食糧や衣服は極端に欠乏し、生産も原材料不足から容易にはかどらず、激しいインフレーションが発生しました。また、食糧不足も同時に加速し、衣類や道具を食糧と交換するなどしてその確保をするのに必死な日々でした。弁当を食べることができない欠食生徒も多く、学校では弁当窃盗事件が起こり、まちでは店頭に並べられたわずかな食べ物も、瞬く間に売り切れていきました。
しかし、敗戦の虚脱から脱する方策も順次推進され、「明るさはまずまちから」と、街路燈が各所に設置され、まちに明るさが戻りました。農村の祭りも開催されるようになり、笛・太鼓の囃子が各地に響き、賑やかに復活していきました。
町内戦没者371人の名を刻んだ碑を建立
戦後、日露戦争により太平洋戦争までの戦没者を刻んだ「殉国戦士之碑」が1954年(昭和29年)に建立されました。川辺町関係者の戦没者は371人にものぼりました。