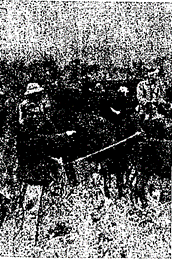足寄町
戦争被害の状況
カゼイン工場の煙突に機銃掃射の跡
1945(昭和20)年7月15日、終戦のまさに1か月前、足寄市街が空襲を受けました。
足寄から隣町の上空を見ると数多くの飛行機が旋回しているのがはっきり認められ、黒い煙がもうもうと上がり、爆発音が足寄まで響きました。やがて、隣町の上空からグラマン2機が足寄に向かって飛来し、そのうち1機が市街地に一直線に突っ込んで来ました。住民たちは、防空壕などに駆け込むなど退避しました。グラマンは、低空からカゼイン(接着剤)の軍事工場(のちの雪印工場)に向かって機銃掃射し、旋回して去っていきました。それ以降、空襲は一度もなく終戦を迎えました。このグラマン1機の空襲は、カゼイン工場の煙突などに数発の弾痕を残しましたが、幸い人畜に被害はありませんでした。
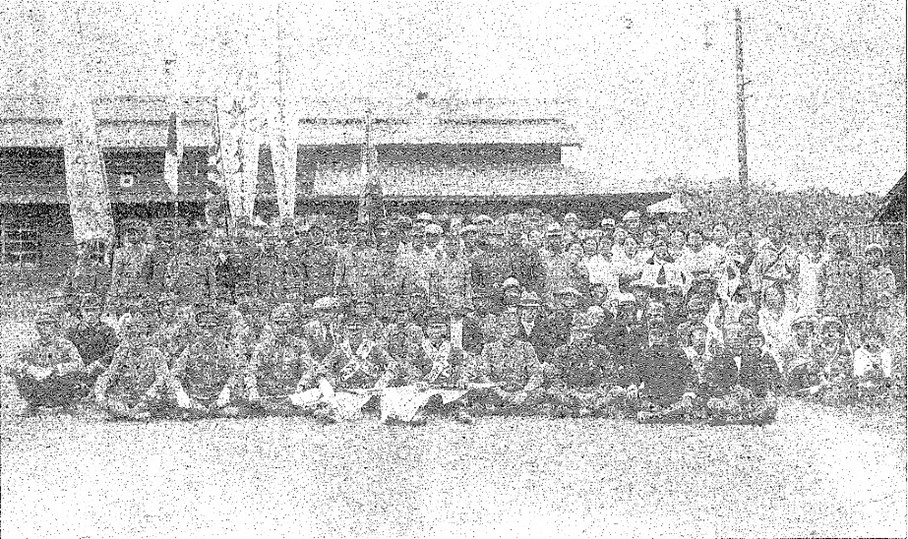
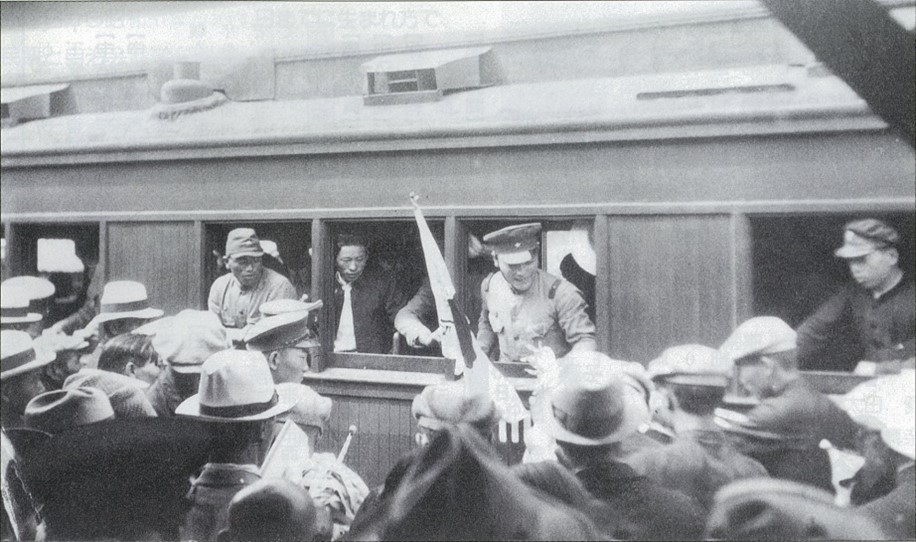
戦後の復興の歩み
生活環境の改善と畜産業の発展
終戦に伴い、復員軍人や外地引揚者が次々と帰国し、足寄地域でも旧軍馬補充部が開放されました。現在の「白糸地区」に帰農した復員軍人43戸をはじめ、多くの人が戦後緊急開拓事業として旧軍用地などに入植したことで、各地域に集落が形成されました。
また、昭和21年から始まった「農村電化」により、農村部への電気導入が進みました。それまで「カンテラ」や「ランプ」を使用していた生活から、各家庭に電灯がつくようになり、町民の生活環境は大きく改善されました。
さらに、当時「限界地帯」といわれていた西足寄地区に本州から和牛を導入する計画が立てられ、昭和26年6月26日に和牛34頭の飼育が開始されました。その後、昭和29年2月4日には上利別駅前で和牛が公売され、昭和30年には市場に出回るようになるなど、本町の畜産業の基盤が築かれていきました。